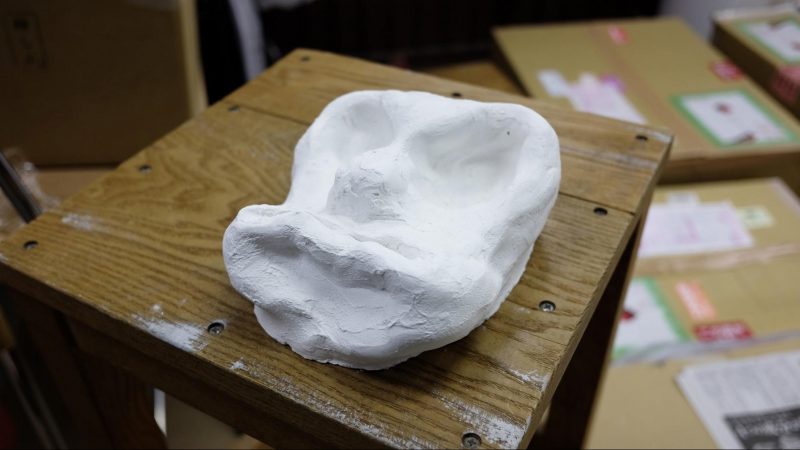ー扱っている素材が伝統のお面というところと、デジタルファブリケーションという新旧のコントラストがすごく利いているイメージがあります。なぜあえて伝統を選んだのか、そしてそれにはどういった意図が込められているんでしょうか?
土岐 やはり伝統は、僕自身のテーマでもあるんです。漆って、伝統工芸的な素材ですよね。僕が学生の頃からずっと考え続けているのは「伝統とは何か」。もし今タイムマシンが存在して、江戸時代にタイムスリップできるとします。今の漆の技術は、大体江戸の後期から明治の初期頃にぐんっと技術が上がり、ピークを迎えているんですよ。それはなぜかというと、輸出の需要、要するに輸出漆器が増えたんです。海外で東洋趣味の物がもてはやされた時期が、ちょうど19世紀頃。その中でも日本の漆芸は最高評価で、ものすごく価値があったんです。その輸出需要に合わせ、西洋の人たちが好むようなデザインに変えて、さらに技術を高めていった時期がありました。今、伝統技術といっている技術が、当時のさまざまな取り組み、新しい材料を取り入れ、ぐんぐんと成長していった時代です。もしそのタイミングに僕らがタイムスリップして、レーザーカッターや現代の道具を持っていけたとしたら、当時の人たちは「こんな物があるのか!?」と衝撃を受けて、絶対に使うと思うんですよね。それは木工ボンドとか、もっと手軽な道具でも。昔は木材の接着に、にかわや植物原料を使っていました。けれどそれを作るのも大変だし、安定的に使うのも難しかったので、もし存在していたら木工ボンドも重宝して使われるんだろうと思います。

土岐 伝統技術の進化の速度は、時代によって早いときと遅いときがあります。現代は工芸的な面では、技術はすごくゆっくり進んでいます。特に日本は戦争もありましたから、戦前やそれまでの社会が作ってきた文化を戦後で線引きしています。それこそ戦前のものが伝統で、戦後のものは伝統に繋がっていないという意識があるため、そこに断絶があるんです。ヨーロッパなんかはそういった断絶がないので、単に古いだけでなく、古い物がだんだんアップデートされていきますよね。伝統はある地点から振り返ったその道筋が伝統と見えているだけで、その道で行われてきていることは、その時代の最新技術との葛藤なんだと思うんです。いいものは定着していくし、だめなものは歴史にも残らないまま消えていく。多分その瞬間にも新しい技術や素材、取り組みとの格闘の痕跡みたいなものが伝統になって、いいものが残っていく。そうだとすれば、今の新しい技術を取り入れて、あれこれするのがあと50年か100年続く。今度はタイムマシンで100年先に行けたとしたら、今の時代を振り返ったときに、もう全てが古いねって感じるんでしょうね(笑)。
一同 (笑)。
土岐 伝統技術だからといって、どこかで線引きして別物だと思うのではなく、今の物だと認識する。今の技術と真正面から向き合って、そういった営みがあちらこちらで行われる。もちろん淘汰されるものもあるだろうし、逆にぎゅって芽が出るものもある。それは多分、未来から見たら伝統になるんだろうな、というのが僕自身のテーマでもあるし、スローガンでもあるんです。いろいろな分野で、それは起こっていると思います。ものを作る、何かを生み出すとき、技術にしても文化にしても、過去をリファレンスするのは必ず必要なことだし、そんな風に考えていけば、伝統に特別注目したいわけじゃないけれど、そこからしか始まらなかった、という自然な発想があるんですよね。
ーそれは先ほど先生が仰っていた、アナログの道具もデジタルな道具もわけ隔てなく扱いつつ、道具としてその軌道にあるものをアップデートする。そして伝統的なものに対しても道具に対しても、真正面から向き合った結果、未来の一歩進んだ表現というものができてくる。
土岐 そうですね。多分僕らが今一番考えないといけないのは、新しい技術を使って作られたものに対する審美眼だと思うんですよね。例えば建築の分野で「ロンシャン礼拝堂は美しい建築だ」と言った場合に異を唱える人はほとんど居ないと思いますし、落水荘の美しさにも一定の普遍的な理解があると思います。じゃあ「ザハの建築はどう?」と言われたときに、すごい好きかすごく嫌いか、みたいな議論に分かれてしまいますよね。そういう好き嫌いではなく、建築の一つの文脈の中であの造形が、例えば代々木体育館に類する美しさなのか、それとも全く別の次元の新しい美しさなのか、という美しさの在りようを議論する必要があると思います。デジタル時代の美意識というのがどういう美意識なのか、その議論をしないといけないフェーズに入ってきていると思うんですよね。本当に美しいのかどうか審美的な話をするには、道具や技術が先行するのではなく、クリエイティビティが先行して、表現だけが評価できる対象になるぐらい、道具や技術が消えるほどに使いこなせないとだめだと思うんです。作品を見るときに、「これはプロジェクションマッピングだな」とか、まだまだ技術は消えていない感じがしますよね。まさに審美的な評価をする時代にこれから入っていくと思いますが、本当に意味のある議論をするときに技術に拘泥していたのでは、審美的な評価には辿り着かないんじゃないかと思います。